あなたもこんなふうに思ったことありませんか?
「何もしない日があると、怠けてると感じる」
「休んでいるのに、心はずっと焦っている」
「疲れてるのに、自分を責めてしまう」
私もずっと、そうでした。

何かしてないと価値がない気がする
“休む=悪” という感覚がずっとあり、
ただ休むことすら、許されていない気がしていたんです。
私は毒親に「ちゃんとしなさい」と言われて育ちました。
大学在学中に心身が限界を超え、
認知行動療法と猫との暮らしの中で、
「休むって悪いことじゃなかったんだ」と気づけました。
この記事では、
「何もしない日」を肯定できた理由と、
心を守るために続けている習慣を紹介します。
この記事を読むことで、
「何もしない日=必要な時間」だと少しずつ受け入れられるようになります。
そして、「もうがんばらなくていいんだ」と、少しでも思えるようになるはずです。

休むことは「心を守る行動」です。
何もしないことに罪悪感を感じていた頃の私
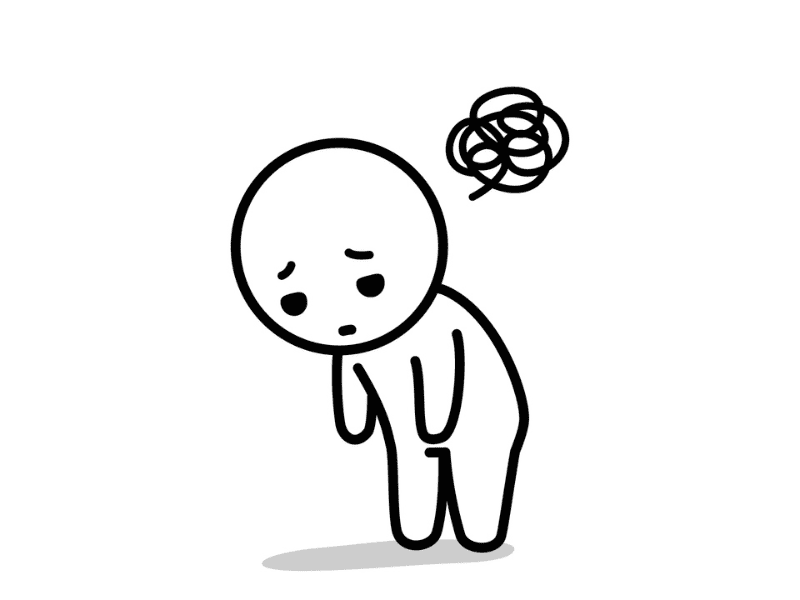
私は、何もしない時間がとても怖かった。
体は動かなくても、
心の中ではずっと「何かしなきゃ」と責め続けていたからです。
特に大学時代や国試浪人の頃、
1日中勉強をしても「まだ足りない」と思っていました。
少し休もうとすると

親に怒られるかも。。。
と、不安がよぎる。
疲れていても毎日8時間以上、机に向かわないと罪悪感が湧いていました。
何もしていない自分を、受け入れることができなかったのです。
「何もしていない」の基準が高すぎて
「1日がんばっても、まだ不十分」
「何か成果を出していないと存在価値がない」
そんな思いが、休むことに罪悪感を生み出していました。
HSPの私は、なぜ「休めない人」になったのか
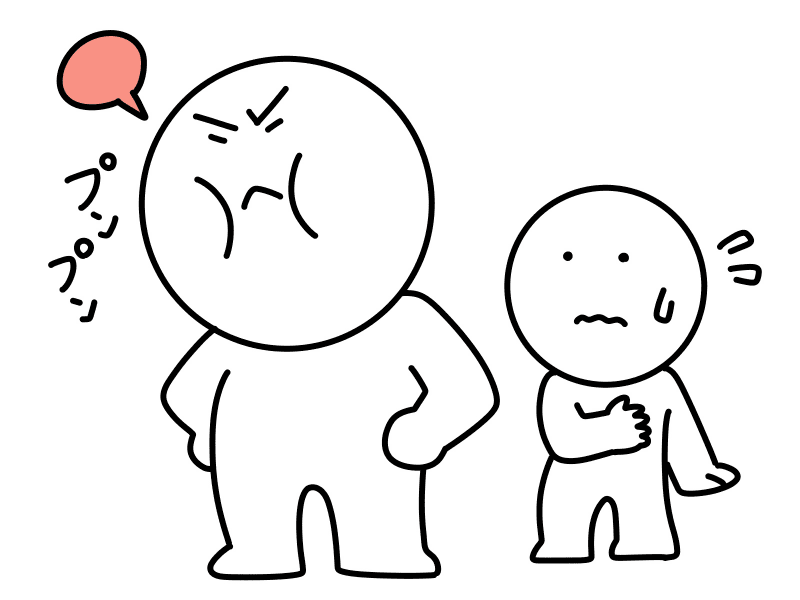
HSP(繊細さん)である私は、人一倍刺激に敏感で疲れやすい性質を持っています。
音、におい、人の気配、言葉の裏――
どれもが過剰に入ってきて、心がすり減るような感覚になります。
でも、周囲の人にはその感覚が伝わらず、
「気にしすぎじゃない?」と言われ続けてきました。
さらに、私は毒親育ちです。
両親は「長女なんだからしっかりしなさい」が口癖でした。
教育方針には「周りに迷惑をかけないように」がいつも隠れていたのです。

「周り=親」だったことに、最近気づきました
頭が痛くて横になると父親に蹴られていたので
「ちゃんとしている子がえらい」
「怠けるのは悪いこと」
そう刷り込まれて育ちました。
だから、疲れを感じても「それを認めること」が許されなかったのです。
「私は弱い」「ダメな人間だ」――そう思うことでしか、自分の疲れを処理できませんでした。
『何もしない日』を肯定できるようになるまで

今でこそ、「今日は何もしない」と決めた日を罪悪感なく過ごせるようになりましたが、
そこまでには3つの転機がありました。
① 完全に動けなくなった日
学生寮のエアコンでフラッシュバックが始まって数ヶ月経った頃。
母に父親との離婚を断られた時期でした。
限界に達したのか、私は本当に「何もできなく」なりました。
食べることも、起き上がることもできない。
布団から起き上がれず、当時彼氏だった夫の助けがなければトイレにも行けません。
もちろん大学にも行けませんでした。
毎朝始業時間になると布団のなかで、
「講義についていけなくなるのはだめなのに」
「卒業できなかったら家族が食べていけなくなる」
動けなくなっているのに、自分に休むことを許せず、責めつづけていました。
② 保護猫との出会い
その1年後に、私は保護猫に出会いました。
その猫は、何もしない。ただ、いるだけ。
ふと疑問が浮かびました。

猫は何もしないのに許されて、
なぜ私は許されないんだろう。
ここまできて「やっと休むことを許せるなんて」と悔しくて泣きました。
でも、そこからやっと「無理しない練習」を始めることができました。
猫の存在は、私の「休みたい」気持ちに気づかせてくれました。
とても尊くて、あたたかくて、私の心を包んでくれました。
「何もしないこと」が生きている価値を損なうわけではない。
「ただそこにいるだけでも、誰かの安心になれる」
そう気づけたのは、その猫と過ごす時間のおかげでした。
③ 認知行動療法で「休むことを許せる」ようになった
親の「早く資格をとれ」というプレッシャーに疲れ果て、心身が限界を迎えたとき。
私は、認知行動療法を勉強し始めました。
そこで「自分を責める思考の癖」に気づき、
「休んでいる=悪いこと」という思い込みが、
過去の経験によるものだと理解できるようになったのです。

頭が痛い子どもを蹴る大人っておかしいよね
「何もしない=怠け」ではなく、
「疲れたら回復が必要」という当たり前の視点を取り戻すことができました。
少しずつ、“休むことを自分に許す”練習が始まりました。
心を守るために私がしている、3つの小さな工夫
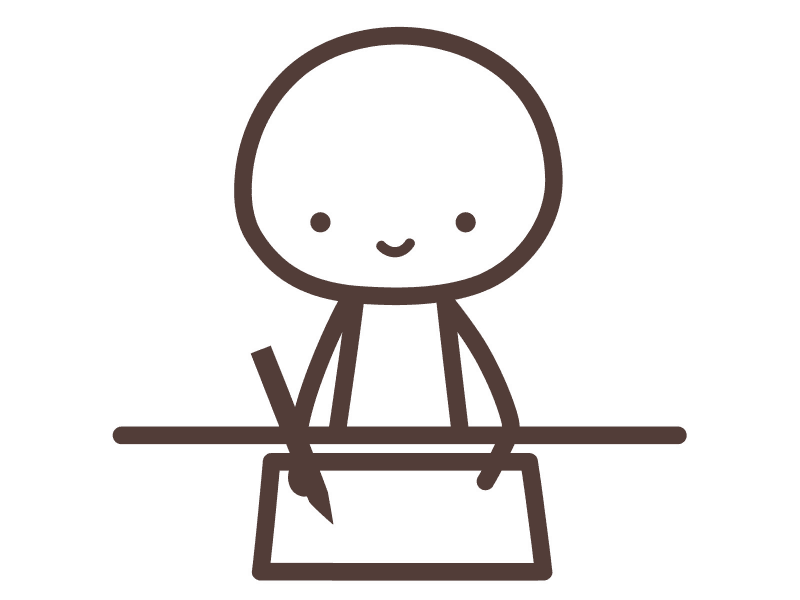
今でも、完全に罪悪感が消えたわけではありません。
でも、心が疲れたときは、意識的に自分を休ませる工夫を続けています。
①「今日やらなくていいことリスト」を書く
ToDoリストの逆です。
あえて「やらないこと」を書き出すことで、自分に“休む許可”を出します。
以前の私は、ToDoリストができないと自己否定が止まりませんでした。

決めたのにまたできていない。
なんでこんなにだめなんだろう。
でも認知行動療法を知り、
「やらないを許す」の視点を持てたことで、
“やらないリスト”を作ることで罪悪感が軽くなることに気づきました。
最初は「やらないことを書いても、気になって手をつけてしまう」ことが多かったです。
そんなときにやらないリストです。
- 今日は洗濯を回さない
- 返信は今日はしない
具体的にするほど気持ちがラクになりました。
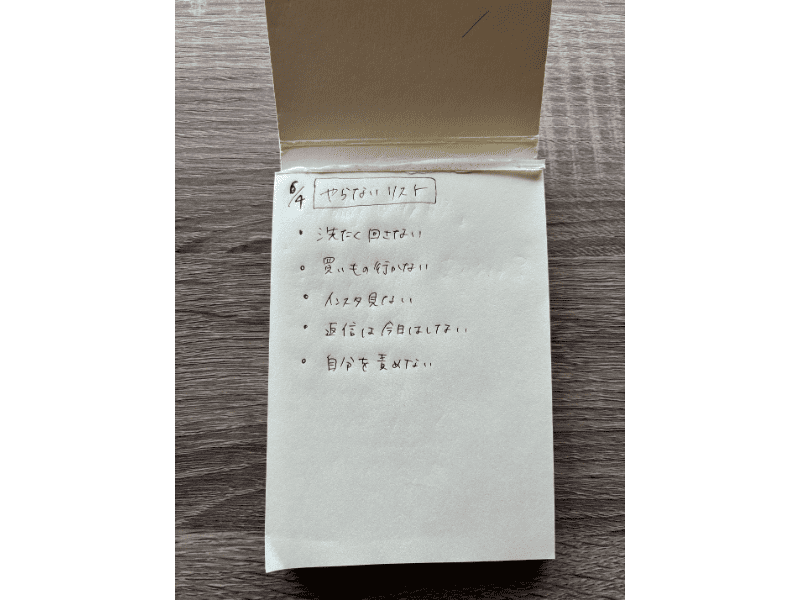
これが今日のやらないリストです。
「しない」と決めることで、安心できることもあると気づき、続けています。
②「何もしない日」を予定に入れておく
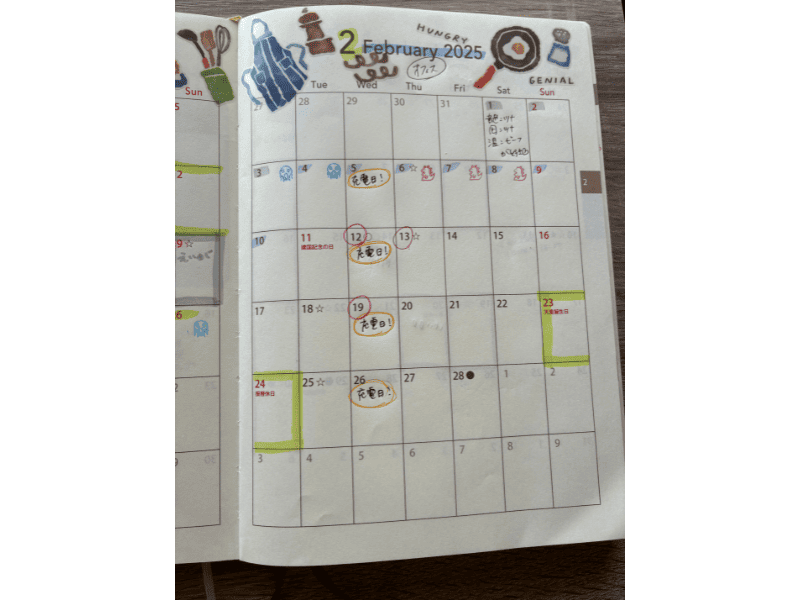
以前は「予定がないと不安」「何か予定がないと落ち着かない」と思っていました。
でもHSPの私は刺激が多いと数日分の疲労がたまることに気づいたんです。
“充電日”と呼んで、定期的に何もしない日を作っています。
予定にしてしまえば、罪悪感が「必要なこと」に変わるんですよね。
「水曜は“充電日”」と手帳やカレンダーに書き込んでいますよ。
③ 1日ひとつだけ、自分をほめる
私は長年「もっとできたのに」と自分を責める癖がありました。
でも、
「しんどいと思いながらでも今日も生きてる」こと自体がもうすでにすごい!
という視点に切り替える必要がありました。
最初は「何もしてないのにほめるなんて」と思い、なんだかむずがゆかったけど
“ちゃんと眠った”と書くことから始めました。
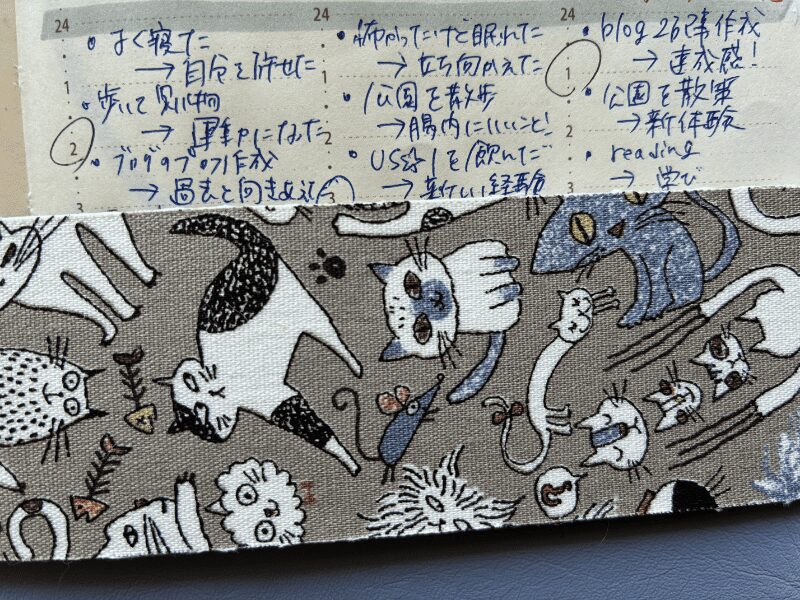
何もしない日でも、自分にこう言います。
「今日、ちゃんと休めてえらい!」
「疲れたってことはがんばった証拠!!」
休んだ自分を肯定する言葉を、毎日ひとつだけ紙に書く。
それだけで、少しずつ自分を受け入れられるようになってきました。
まとめ|「何もしない日」は、あなたの心を守る大切な時間
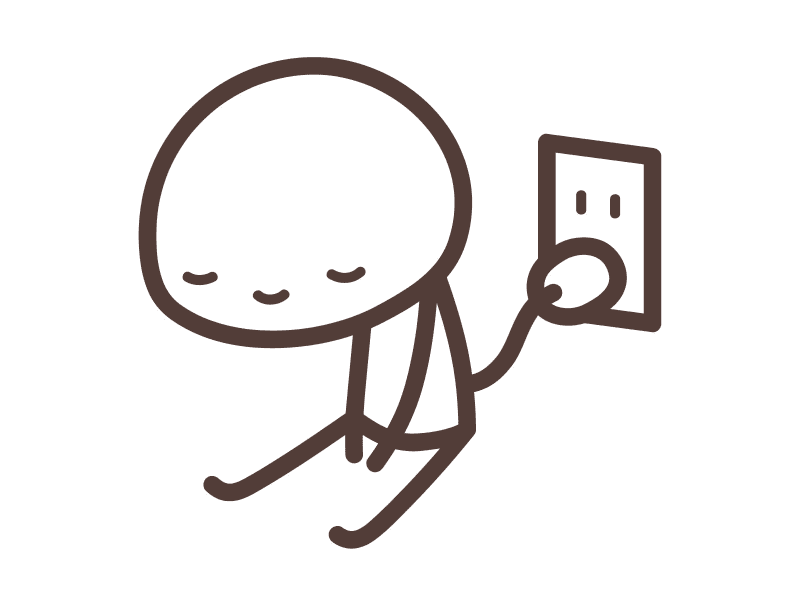
「何もしない日」に罪悪感を感じていた私が、
認知行動療法を通して「休む=悪じゃない」
と気づけるようになりました。
何もしない時間は、怠けではありません。
「心の回復に必要な行動」です。
もしあなたも、
「何もしていない」とモヤモヤ中なら――
どうか、その気持ちを責めずに、
まずは一度立ち止まってみてください。
「休む勇気」を持つことが、
本当の意味で自分を大切にする一歩です。
今日だけでも、
なにかを「しない」ことを、ゆるしてみてくださいね。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

私はまだまだ“休むこと”を練習中です。
あなたの「こんなときどうしてるよ」も、
ぜひ教えてもらえたらうれしいです。
小さなことでも、気軽にコメントやお問い合わせくださいね。
あなたの心が、すこしでも軽くなりますように。
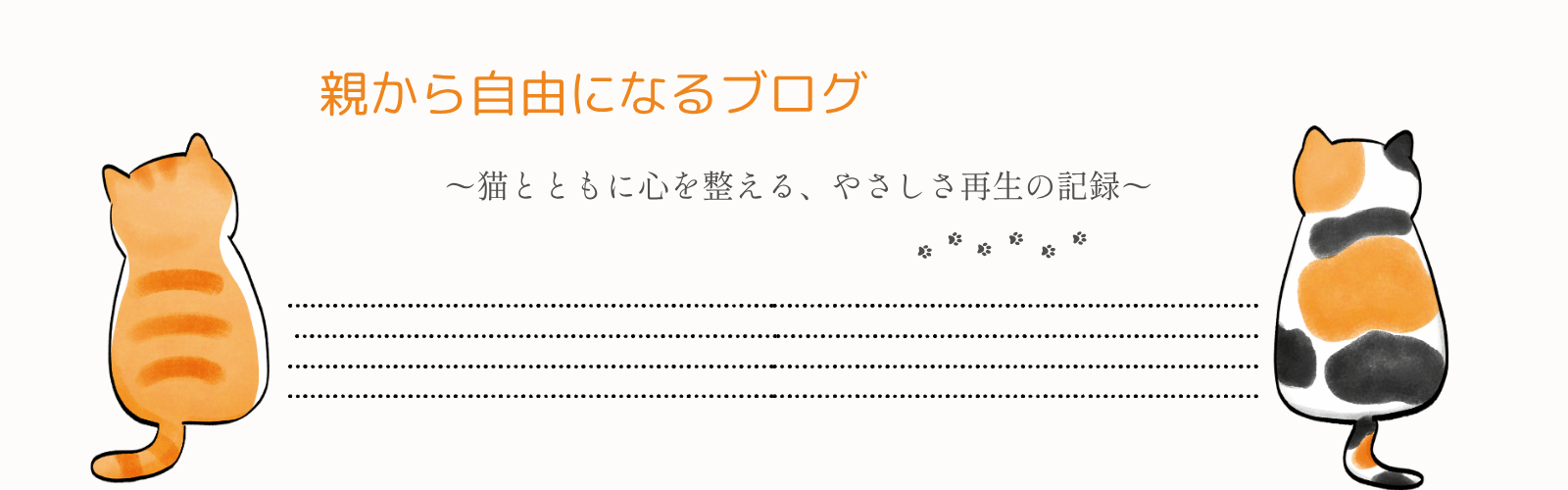
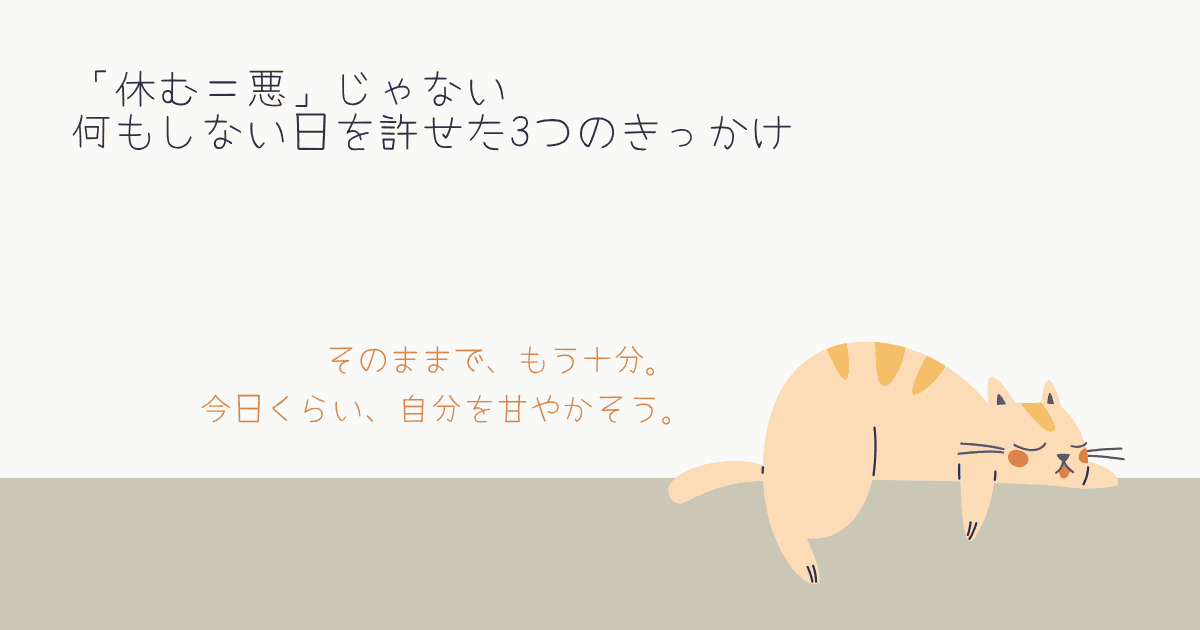

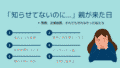
コメント